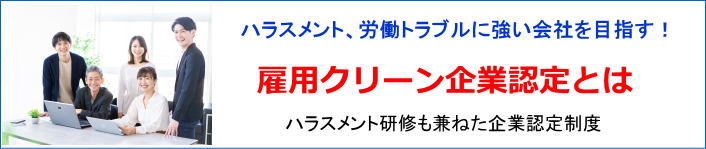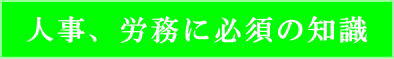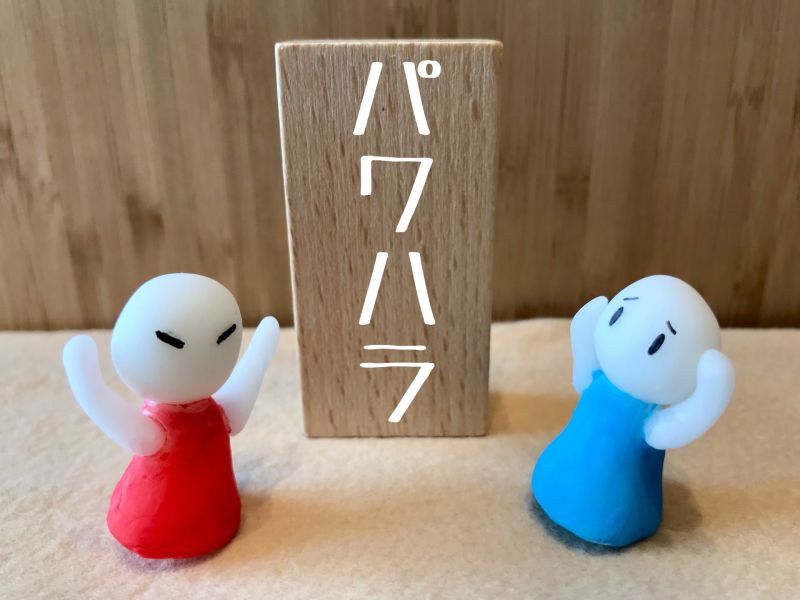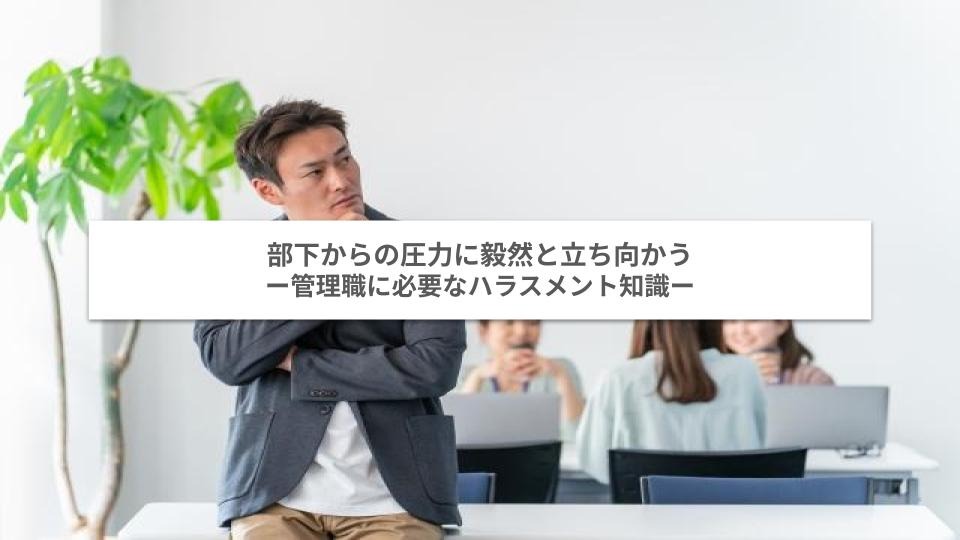パワハラをしている自覚がない理由
経営者からその会社の幹部クラスの社員に関する相談を受けたり、会社員から上司との関係に関する悩みの相談を受ける中で感じるのは、自分がパワハラをしてる自覚のない人が多いということです。
自分がパワハラをしている自覚がない人は、平気で下記のようなことを言ったりします。
「部下からパワハラだと思われる発言をする奴は、俺の力で降格させるから気を付けろ!」
この発言は、部長からその下の中間管理職に向けた言葉ですが、思い切りパワハラです。
社内でパワハラを生まないという目的に正当性があったとしても、自分の立場や権限を振りかざして、脅迫めいた言葉で指示をするということはパワハラにあたります。
このようにパワハラをしていることを自覚していない人は、目的としては正当性があることを相手を脅すような言葉で伝えていたり、脅すような言葉で部下の行動を促したり、抑止させている傾向が強いと言えます。
自分は正しいと思っているからパワハラに気づかない
上記のような上司は、自分の言動の目的には大義名分があると思っています。
その上で、自分が伝えたことが部下に浸透しなければ、部下の理解力不足だと思っているため、伝え方を工夫しようという発想はありません。
さらに、これまで自分の権限を振りかざして、強迫的な言動で部下に指示を出して結果が伴ってきたという勘違いも含めた実績があります。
これらの理由から、自分の発言がパワハラにあたると気づかないのです。
しかし、自分の地位や出世、社長からの評価には固執があるので、社長から部署内で上司からパワハラを受けたという訴えが出ないようにという警告があると、自分のことは棚に上げて部下に対しては言動を厳しく注意し始めます。
無知な人ほどパワハラをしてしまう
無自覚にパワハラをしてしまう人は、無知であるという特徴があります。
無知な人は、どのような行為がパワハラにあたるのかを知らないため、自分の普段の言動がパワハラにあたると気づくことができません。
さらに無知な人の特徴として、知らないことを知ろうとする習慣がないのです。
例えば、会社を上げてパワハラを出さないようにしようという方針が出たとしたら、まずはどのような行為がパワハラにあたるのかを確認する人は、パワハラということに対して知識を得ることができます。
しかし、無自覚にパワハラをしてしまう人は、どのような言動がパワハラにあたるのかを確認しようとしない傾向があります。
このようなタイプの人は、部下から上がってくる話は貴重な情報だという自覚もないため、部下とのコミュニケーションでも十分に話を聴かずに自分の主張だけを伝えます。
そして高圧的に自分の要望を伝えようとするので、部下にパワハラだと感じさせやすいと言えます。
パワハラをしてしまう人は言語力が低い
もう1つ無自覚にパワハラをしてしまう人の特徴として感じられるのが言語力の低さです。
言語力が低いため、自分が相手に伝えたい事柄を相手が受け取りやすい言葉に加工して、相手が受け入れやすいタイミングや順序で伝えることができていません。
どうしても短絡的かつ、攻撃的な言葉で思いを伝えることになるため、相手には威圧的に捉えられパワハラという印象を与えてしまいます。
管理職には、良いアイデアや行動力がある人でも、言語力の低さのために組織にアイデアを浸透させたり、部下の行動力を促進することができていない人もいるので、管理職になる人は言語力を高める意識を持ってほしいと思います。
パワハラは企業の成長を止める
パワハラをする管理職がいるということは、そこで働く人たちが不必要な心身の負荷を受けながら働くことになるので、個人の尊厳や健康を侵害するという点で問題です。
そして、その企業で働く人にとって働きにくい職場であるということはパフォーマンスを十分に発揮できない職場であり、人材が定着しにくい環境だということでもあります。
パワハラという問題は、そこで働く個人の問題だけでなく、企業の成長を損なうという問題でもあるのです。
無自覚にパワハラをしている管理職がいる職場では、社員が上司の顔色を伺って仕事をしています。
パワハラをする人は自己保身が強いという傾向があるので、部下が仕事で挑戦をしようと思っても上司の性格を考えると行動を起こしにくい雰囲気があります。
また、能力が高い社員ほど、自分の力を発揮できる環境を求めて転職を考え始めます。
管理職の無自覚なパワハラは、その管理職の人が気づかない間に企業の成長という観点からもマイナスになる要因を生み出してしまいます。
企業を成長させるためには、パワハラをどのように無くしていくかということは1つの戦略として取り組んでいくべきことでもあるのです。
 個人で雇用クリーンプランナーを取得したい方へ |
 |
■関連記事一覧