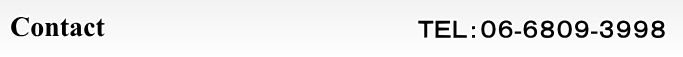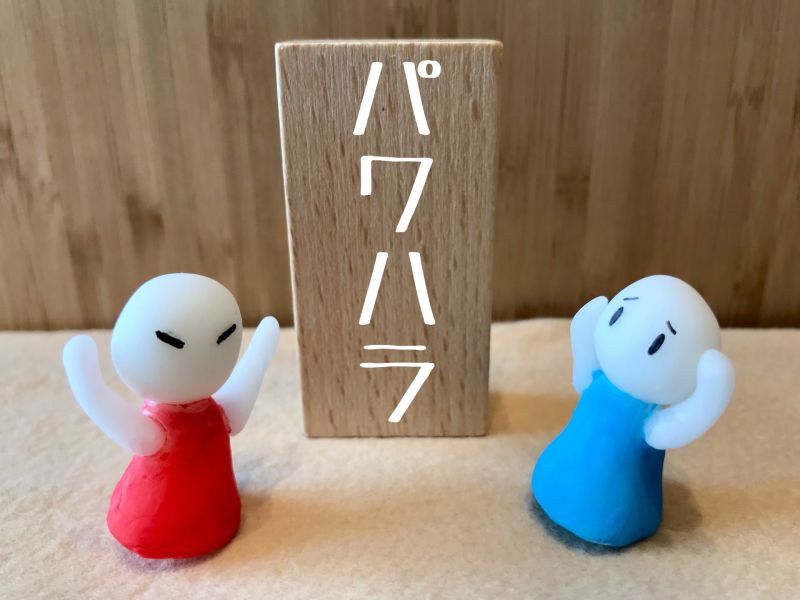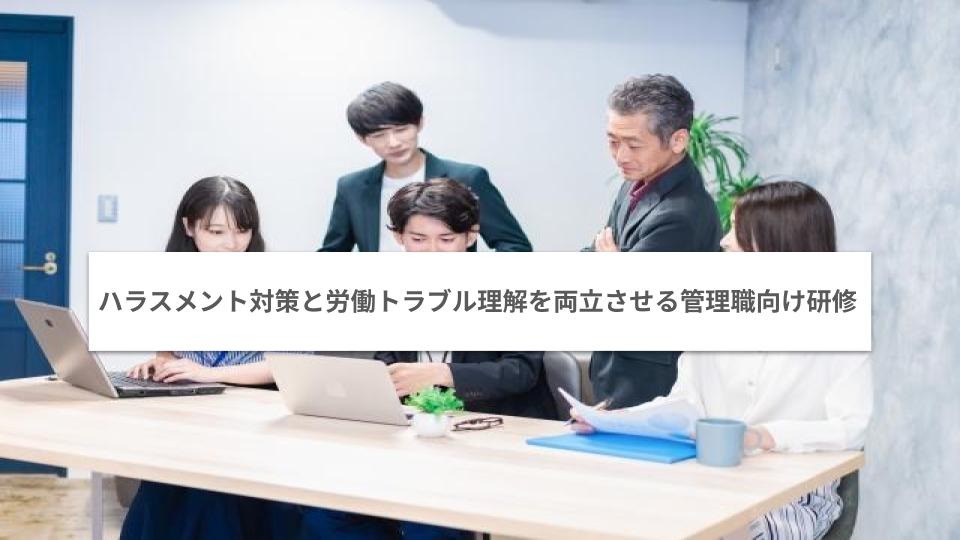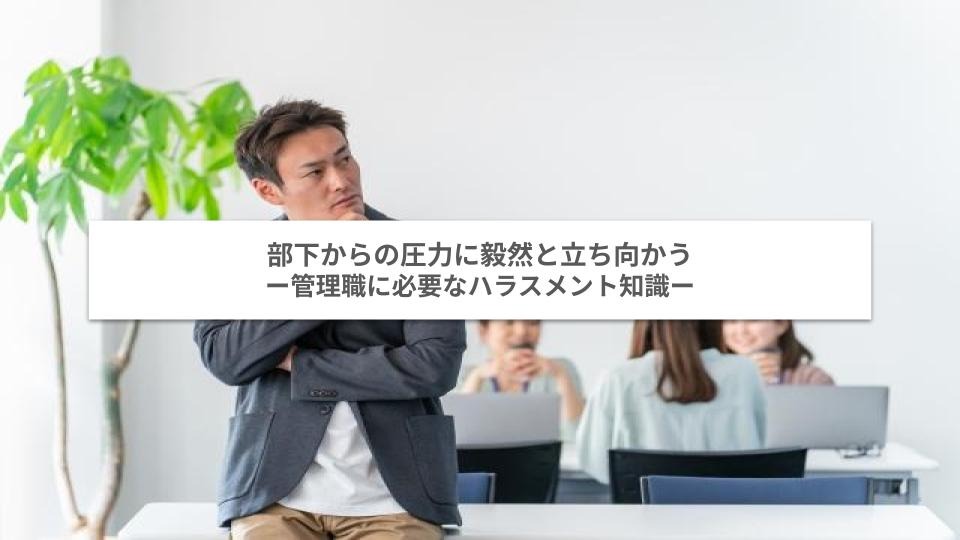5月29日、職場でのパワーハラスメント防止を義務付ける法案が国会で可決・成立しました。
パワーハラスメント(パワハラ)を「優越的な関係を背景にした言動で、業務上必要な範囲を超えたもので、労働者の就業環境が害されること」と初めて定義し、企業には相談窓口設置や、パワハラを行った従業員の処分内容を就業規則に記載することなどが義務づけられるなど、これまで以上に丁寧な対応が求められることになります。
パワハラの判断基準とは
ご参考までに、厚生労働省はパワハラを判断する基準として次の6類型を定めています。
- 身体的な攻撃
例)叩く、殴る、蹴るなどの暴行を受ける。丸めたポスターで頭を叩く。
- 精神的な攻撃
例)同僚の目の前で叱責される。他の職員を宛先に含めて罵倒される。
必要以上に長時 間にわたり、繰り返し執拗に叱る。
- 人間関係からの切り離し
例)一人だけ別室に席を移される。強制的に自宅待機を命じられる。送別会に出席させない。
- 過大な要求
例)新人で仕事のやり方もわからないのに、他の人の仕事まで押しつけられて、同僚は皆先に帰ってしまった。
- 過小な要求
例)運転手なのに営業所の草むしりだけを命じられる。事務職なのに倉庫業務だけを命じられる。
- 個の侵害
例)交際相手について執拗に問われる。妻に対する悪口を言われる。
パワハラの調査結果
厚生労働省のデータによると、各企業が設けている相談窓口での相談テーマで一番多いものは、パワーハラスメントです。
(平成28年度職場のパワーハラスメントに関する実態調査より)
? パワーハラスメント 32.4%
? メンタルヘルス 28.1%
? セクシュアルハラスメント 14.5%
パワーハラスメントに関する相談内容については、「精神的な攻撃」(73.5%)
加害者と被害者の関係では、「上司から部下へ」(77.3%)
これらの比率が最も高くなっています。
また、<パワーハラスメントに関する相談があった職場に当てはまる特徴(複数回答)>として、
? 上司と部下のコミュニケーションが少ない職場 45.8%
? 失敗が許されない/失敗への許容度が低い職場 22.0%
? 残業 が多い/休みが取り難い職場 21.0%
というデータもあります。
近年パワハラは大きな社会問題となり、自殺してしまう人まで出ています。
「パワハラ」や「セクハラ」など、いわゆる「ハラスメント」は社会全体で真剣に向き合っていかなくてはなりません。
しかし中には、「ハラスメント」という言葉が一人歩きし、例えば社内で上司が適切だと考えた範囲で部下を注意したことが「パワハラだ!」と言われてしまうこともあるようです。その結果上司は何も言えなくなってしまい、そして部下指導することを敬遠しがちになってしまう、という本末転倒な状況になっているというお話を伺うこともあります。
しかし、自社で採用したスタッフに成長してもらうには、指導が必要です。
「何でもパワハラと言われるから・・・」という理由で何も言わない、というのは企業にとってマイナスでしかありません。
先に述べた様に、
「上司から部下」へのパワハラ相談が8割近くあること、
上司と部下のコミュニケーションが少ない職場にパワハラに関する相談が多い、
ということから、「上司と部下の関係」にハラスメント防止のヒントが詰まっているように思います。
どんな言葉がパワハラにあたるのか、何をやってはいけないのか、など1つ1つ詳細に挙げることは難しいことです。そればかりを考えていては、確かにコミュニケーションが取りづらい環境になってしまいます。
「ハラスメント」を完全防止することは難しいかもしれません。
しかし、努力することはできます。
特に、企業に於いては、上司から部下への働きかけは絶対に必要です。
上司が今の若者の考え方を知り、それに対応していかなくてはなりません。
これは決して「甘やかす」ということではありません。
「若者のことを知るために、自分の時間を使う」
「部下のために少し頑張ってみる」ということです。
「お互いを知る」時間を作ってみませんか
「最近の若いもんは」という言葉が聞かれますが、ある説によると、古代エジプトの時代から、この言葉は使われていたそうです。
どんな時代も自分より下または上の世代については分からない、ということが言えます。
つまり、「上司は部下が理解できない」、「部下は上司が理解できない」、これは当たり前のことなのです。
そして、この「当たり前だ」という認識をそれぞれの世代が受け入れ、「どんな違いがあるのか」を知ることに時間をかける努力を、お互いがしてみてはいかがでしょうか。
例えば、
入社前交流会として新入社員と、社内の各世代が集まり、これから社会に出る新社会人はこういう場面ではどう行動するのか、あるいは何を考えるのか、など仕事上の例をいくつか挙げてみて、それぞれの世代が「自分ならこうする」「こう考える」という意見を出し合い、「違いを知る」時間を作ってみてはいかがでしょうか。
この時、やってはいけないことは「相手を否定する」ということです。
新社会人は仕事については何もわかりません。例え、非現実的な話が出たとしても、それを頭ごなしに正すのではなく、「そうか。今の若者はこう考えるんだ」といったん受け入れます。
それから、「仕事では私達はこうしている。入社したら一緒にやってみよう。」と社会に出てから指導されることが当たり前、だという認識を新入社員に持ってもらうのです。
「コミュニケーション」は「ハラスメント」のひとつの防止策
「お互いを知る」ためにはコミュニケーションが必要です。
コミュニケーションが日々行われれば、お互いが何を考えているのか、理解しやすくなります。また、その人が発する言葉の意味を想像したり、直接尋ねたりすることがしやすくなるでしょう。
お互いのことを大切に考えることができれば、発する言葉にも気を遣うようになります。(どうでもいい人には言葉を選ばないように思います・・・)
自分自身の「気持ち」を伝える時に、相手を思いやり、言葉を適切に選ぶことができれば、「ハラスメント」を必要以上に恐れることはなくなると信じております。
かなり粘り強く続ける必要がありますし、本当に時間、手間のかかることです。
そして、「これだけが解決策」、というものがないのも現状でしょう。
しかし、できることからやってみることで、何かが見えてくるはずです。
AXIAでは例えば上司の方々を対象に「聴き方」や「伝え方」を実践しながら理解していただく研修も行っております。
私どもがお手伝いできることがあれば、ぜひお気軽にお声掛けください。
 |
伊藤香子/いとうきょうこ
企業の人材育成を目的とした各種研修を担当しています。 主に行っているのは、階層別の研修、新入社員研修、コミュニケーション能力向上、モチベーションアップ、メンタルヘルスの基礎、ハラスメントに関する研修など。 コンサルティングとして年間を通じた企業の研修スケジュールの立案も行います。 また個人のキャリア構築を支援するためのキャリアカウンセリングでは、社内でのキャリアパスや転職などのビジョンを明確にするためのサポートを行っています。 資格 国家資格キャリアコンサルタント |