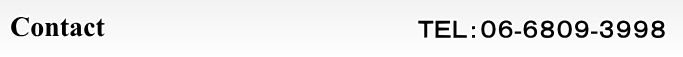今回の記事は、成長しない社員についてです。
人材育成に関する相談を受ける中で、年齢にあった思考や振る舞いができない社員、わかったふりをしているけど仕事の方法や要点を理解しない社員の存在に悩んでいる経営者が多いということを感じます。
上記の2つのパターンに当てはまる人の特徴として、時間が経っても成長の跡が見られないというところが共通しています。
成長しない社員の特徴
では、なぜ成長しないかというと、それは年齢に不釣り合いな幼さを持っているということだと思います。
年齢にあった思考や振る舞いができないというのは、周囲の人が自分に何を求めていて、どういう言動をとることが望ましいかということよりも、自分はどのように振舞った方が得かを浅はかに考えているのかもしれません。
また、わかったふりをしているけど仕事の方法や要点を理解しないというのは、本当に自分が必要なことを理解するかどうかより、相手が自分が必要なことを理解していると思ってくれているかどうかという点に価値基準を置いていて、相手からの承認を時間を掛けて努力した結果によって得るのではなく、実際に能力が向上したり理解度が高まったということより、現実はどうであれ相手に自分をどう評価してもらうかという、浅はかな承認の求め方をしていると感じられます。
社会人として、他人に自分の労力によって生み出した価値を提供するという感覚が乏しく、無意識で与えてもらうことを求めているような幼さを成長しない人から感じられます。
成長しない社員が抱える心理的特徴は親子関係で作られている
上記のような特徴がある人は、家庭環境に以下のような特徴があると思われます。
- 親が世間体を気にしていて、自分自身がどうかよりも社会にどう思われているかという視点から子供の振る舞いを指摘したり、評価している。
- 子育てに対して一貫した方針はなく、親に不安や不満を与えなければいいという雰囲気があり、子供自身のためになる努力に関心も弱いし評価もしない。
- 親が刹那的な考え方で、欲求や感情のコントロールが苦手なため、子供に求めていることを親自身ができていないことが多い。
上記のような特徴の家庭で育つと、自分の本心に対する関心よりも周囲にどう思われているかという意識が強い、自分のために必要な努力が何か判断できない、欲求の満たし方が刹那的で浅はか、というような特徴が強くなり、現実を見据えた判断と行動ができない大人になってしまう可能性があります。
社会に出るには、少なからず周囲に貢献できる力を備えている必要があり、それを向上させていく能力が求められますが、それが掛けている人が部下にいると、必要なことを教え、重要なことは何度も伝えているのにその部下が成長しないという悩みが生じます。
自己成長力のない部下の育成方法
では、自己成長力を持っていない人を会社の中で育てるにはどうすればいいのでしょうか。
努力目標の設定
私は、極論を言えば上司や先輩が、子育てと思ってその人と関わることが必要だと思います。
自己成長力を持たない人は、別の言い方をすれば非常に依存的な思考が強いので、子育てと思って関われば必ず自己成長力が育つ保証があるわけではありませんが、依存的な思考が強いからこそ子育てのように関わることが望ましいと言えます。
それは具体的にどのようにするかというと、その人が少し努力すればクリアできそうな小さな目標を設定して、それをクリアすれば褒める。
そして前回よりも少しだけ高い目標を設定して挑戦させる、ということを繰り返すという方法です。
取り組みを評価する
これだけだと、普通の人材育成方法でも同じような方法だと思われるかもしれませんが、その違いは設定する目標は結果ではなく、結果は伴わなくても求めた努力をすればいいという基準になります。
例えば、売上を上げるために必要な行動があるとしたら、その行動を決められた期間継続できれば目標達成であり、その行動によって売上が上がっていなくても、その点には目をつむるということです。
それはなぜかというと、自己成長力のない人は、これまでに伸ばしてきた能力が少ない、もしくは低いので、他の人と同じ行動をしても現われる結果に差が出てしまうのです。
その人がこれまでに能力を向上させていないことを指摘しても仕方がないので、まずは必要な行動を継続できたかを評価してあげ、あとはそれに伴い能力が向上してくれば結果が出る、と励ましながら関わっていくことが大切です。
忍耐力を持って関われるかどうかがポイント
子育てでは、早くいろいろなことができてほしいと望みつつ、子供が自分で歩いたり、言葉を話したりすることを待ちながら忍耐強く関わっていくと思いますが、自己成長力の弱い部下には同じような感覚を持って関わることが必要だと思います。
そのような意識を持っておくことが、組織の人材育成能力を向上させることにつながるので、自己成長力を持っていない部下の存在が組織の人材育成能力を向上させてくれると思って関わってみてはどうでしょうか。
職場の事情、職業によっては、一定のレベル達するまでにどれだけの猶予を持てるかということが変わってくるので、闇雲に忍耐力を持って待つというわけにはいかないと思います。
職場の事情や職業との兼ね合いで、どこまで待てるかということも踏まえた上で『ここまでは待つ』と腹をくくって関わることが人材育成には必要になります。