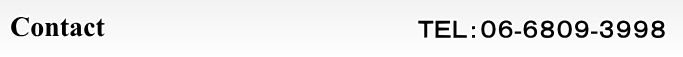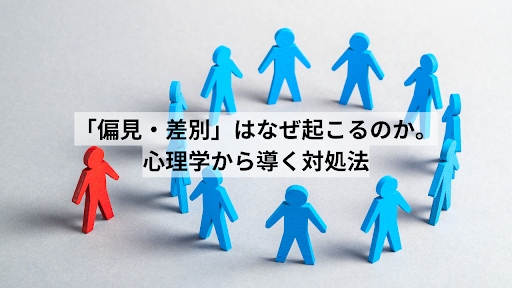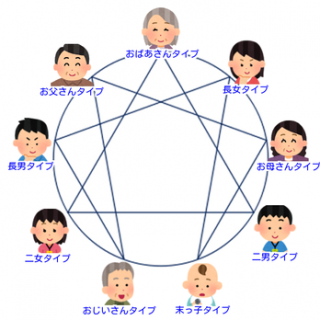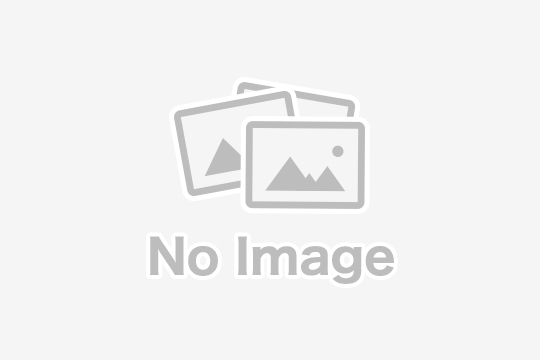情報伝達のスピードを維持する
組織の中ではさまざまな情報が行きかっています。
組織内では、そこに属する人がその情報の伝達スピードを落とさないようにするという意識が大切になると考えています。
情報伝達のスピードが遅いとどうなるか、いくつか例を挙げてみたいと思います。
決断を促された時
ある行動をするのかしないのか、いつ動くのかなど、決断をする必要があり、その決断が自分以外の人にも影響を与える時、すぐに決断をする、決断を迷っていることを伝えるなど、決断ができるにしてもできないにしてもその状況を伝えることが大切です。
決断を待っている人がいるのに、決断できずに迷って何も意思表示をしなければ待たされている方の時間は無駄になってしまいます。
疑問を感じた時
仕事の中で疑問を感じた時、疑問に感じていることがあるという情報発信をする必要があります。
疑問に感じたけど、『まあいいか』と疑問を自分の中にしまい込んでしまう人がいますが、その疑問に感じた部分が業務に支障をきたしたり、何らかのロスを生んでいるものであれば、早い段階で解決をする必要があります。
他にも組織内では、伝達すべき情報がたくさんありますが、個人の判断で埋もれている情報も少なくない可能性があります。
情報伝達のスピード感を共有する
組織内の人が、同じスピード感と情報伝達の重要性を理解していれば、テンポよく情報が行きかうようになりますが、スピード感は放っておくと統一されません。
なぜなら、それは人の感覚であるため個人差があるからです。
人によって早いと思っていても、別の人には遅いと感じていることもあります。
そのため、上司が『なるべく早く知らせて』という指示を出して、部下が早い方が良いと理解して次の日に情報を伝えたのに、上司から『遅い』と叱られる、というようなことが起きるのです。
このようなことを無くすためには、この組織の中で求めているスピード感はこれだ、と全員が同じ認識を持てる指標が必要になります。
組織内でスピード感をそろえるには、下記のようなことを徹底することが良いのではないかと考えています。
- 指示を出す時にいつまでに行うかを明確に伝える
- 指示を受けた時にいつまでに行うべきかを確認する
- 判断に迷っている時は迷っていることを伝える
- 疑問があれば、答えを知っていそうな人に即確認
- その日のメールはその日のうちに返答
他にも工夫できることはあるかもしれませんが、上記を組織に属する人全員で共有すれば、スピード感のズレはある程度整えることができ、情報伝達のスピードが保たれるし、スピードが落ちていると感じた時は、上記を再徹底することで調整し直すことができます。
サッカーで例えるなら、テンポよくパスが回ってゴールにたどり着くような情報伝達ができる組織作りが望ましいと思っています。
人材育成サポート